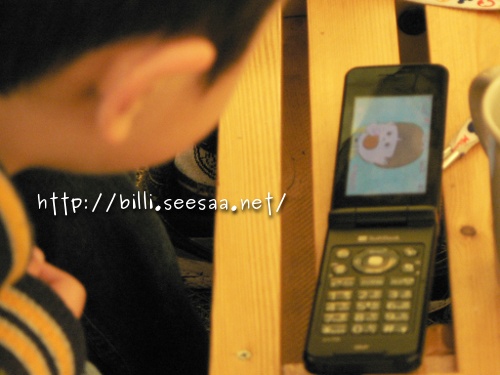とことん山キャンプの続編です。

今回の焚き火には「チャレンジ」と「遊び」と「癒し」がありました。いつものように教科書どおりハントマンで木を削ぎ、火をつけやすくしました。実は木を削ぐ以上に簡単に着火させる方法も学びました。新たな遊びも発見?しました。 子どもたちは終始、焚き火に色めき立ちまくってましてね(笑)。興奮気味の子どもたちを見守りながら、癒されながら、長~い時間焚き火に惹きつけられ「炎への興味ってDNAレベルに刻み込まれてるんでしょうかね」みたいなことを感じました。
子どもたちの焚き火への興味
「お父さん焚き火したい」というボクちゃん。なんで?と思いながら振り返ったのはこのキャンプのこと。リンク先の記事にはありませんけど、実は初めてハントマンで木を削ったこの日、ナイフで拾った薪を薄く剥ぐことにもチャレンジしました。火を付きやすくする例のヤツです。そして当然、その薪に火を着けて遊びました。その記憶が「焚き火したい」発言につながったのかなぁと。
焚き火の着火作業

この薪で着火させるつもりはなかったんですけど教科書どおりに薪を削ぎました。ナイフを使う練習ですな。ナイフを扱うお兄ちゃんの手つきにも少し安心感を覚える程になりました。

着火マンをカチッとするだけのチカラがないボクちゃん。ビリと一緒に着火します。 トーチを使って着火する方が断然速いし、間違いなく簡単なはず。ですけどビリ家では着火作業そのものを一つの勉強・遊びだと思っています。

新聞紙やら拾ってきた細い枝を投入して着火を試みます。瞬間的に小さな炎になりますが持続せず。

試行錯誤の末、杉の葉をメガ盛りすることに。杉の葉の下に隠れている新聞紙に火をつけると・・・

大量の煙を吐き出しながら・・・

みるみるうちに炎があがりました。

「杉の葉って火が付きやすい」という実体験を得た子どもたちは、自分が投入した杉の葉の燃える様子が面白いようで、これでもかと繰り返し杉の葉を投入。 きっと杉の葉が着火剤として使えるということが記憶に残ったことでしょう。良い勉強になりました。
焚き火で色めき立つ子どもたち

着火作業ですでに十分過ぎるほど安定しまくっている炎に、やっと薪を足していきます。燃え上がる炎に子どもたちの表情も興奮気味。

炎の熱にやられて半袖になり、一気にハイテンションに。 こんな子どもたちの様子を見ていたら、ふと「焚き火」はわが子を伸ばす四大必須科目と考えられていることを思い出し、この考えは間違いないなと妙に納得。
焚き火を使った新たな遊びの発見

ゆらぐ炎をみつめ癒しを感じていると。

ボクちゃんは、炎の熱でイカれた頭を押さえながら燃え盛る炎に木の枝を突っ込みはじめました。木の枝の先に火を着けようという意図です。 子どもたちは、炎への恐怖を感じ警戒しながらも上の写真のような行動に現れているとおり警戒感が徐々に薄れていくようでした。その様子が親目線には「危ないなぁ」と映る。けど、こちらから「ダメ」と制することはしないように努めました。子ども自身が、やっていいコトとダメなコトの境界線を見つけるべきだと感じていました。

そんな親の思いとは無関係に子どもたちは枝の先についた炎を振り回して遊びはじめました。肉眼でも上写真のように見えましてね。写真に撮ったらこれまた面白い。新たな遊びの発見です。

子どもたちは薪が燃え尽きるまで、こんな名前もつけ難い単純な遊びに興じました。こんな遊びに何か意味があるのか。そんなこと考えてもわかりません。でも、子どもたちは他の遊びではあまり見られない満足げな表情をしていました。